モンゴル草原横断録 -後編ー by 弘實 和昭
- 2016.10.10
- 暮らしの風景
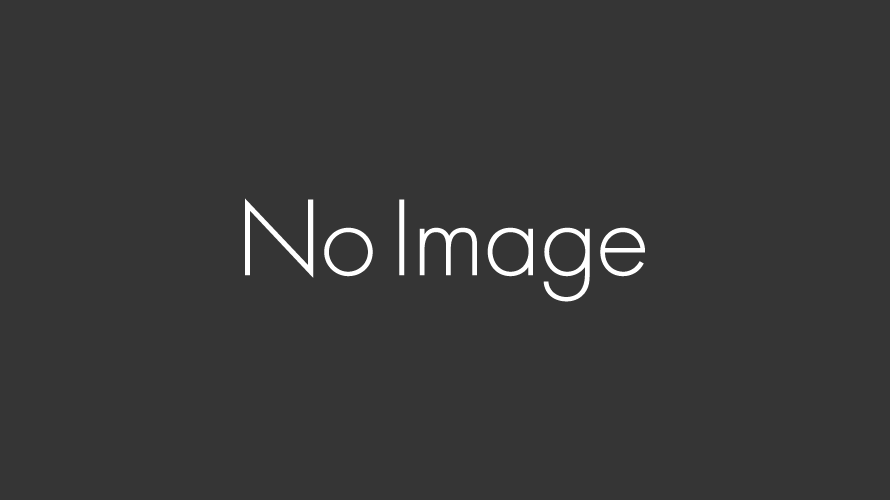
☆ お待たせいたしました。8月7日の記事(同タイトル前編)から続きます。
翌日は、ウラン・バートルから南へ580km、ゴビ砂漠を横断して南ゴビの中心都市ダランザドガドへと向かう。途中、中央ゴビ県のマンダルゴビで昼食を取る。まっすぐに走っている舗装道は新しく、かなり快適で凸凹もほとんどない。

澄み切った青空と緑の草原、白い雲と遠くのきれいな山並み、乾いた涼しい風。モンゴルの原野はすこぶる気持ちがよい。どんなに写真が下手な奴でも、撮った写真は部屋に飾って置きたくなるほどの出来栄えになってしまう。この風景では駄作を撮ることなど出来ないのだ。車を降りて新鮮な空気に触れるとハーブの香りがした。夏の草の匂いである。
日本人はゴビのことをゴビ砂漠と教わり、砂漠であると信じているが、モンゴル語のゴビという意味は「草がまばらに生え,若干の動物が生息する荒れ地」を意味する。もちろん日本語には該当する言葉はない。
ゴビの乾燥した土地に生えているイラクサと名付けられたヨモギのような草を家畜は食べない。触ってみると痛い。この牧畜にはあまり適さない原野を、それでも家畜たちは通り過ぎていく。遊牧が極めて過酷な生活であることは、ゴビを見れば理解することができる。

その草原と砂漠の入り混じった平原でも、家畜たちはのんびりと草を食む。よく見ると、草の間にはスナネズミやウサギ、リスたちがいて、想像以上の小動物たちの宝庫である。その小さな動物を狙って、ノスリやハゲワシなどの猛禽類が狙いをつけて睨んでいる。この少し荒涼とした草原は、都市生活者である我々人間には不毛なる大地としか見えないのだが、鷲たちにとっては食べ物の並べられたテーブルに見えているはずである。どんな地域にでも食物連鎖があり、その地域特有の生態系が確立する。このことを感じ取れる風景が目の前に表れていた。さらに進むと、ヒツジの死骸にハゲワシが群がっている。そして草むらに交じって家畜の白い骨が所々に転がっていた。
ガイドをしてくれたエコツアー会社のトゥメンさんは驚異的に視力が良く、遠く離れた山の稜線のアイベックス(ヤギの仲間)ガゼル(牛の仲間)や鷲など、すぐさま見つけてしまう。ランドクルーザーを運転しながら車の前を素早く横切る小鳥たちの名前も瞬時に判断して車を止め見せてくれた。
草原のトイレタイム。おしっこは地平線に向けて元気よくシャーと発射。馴れてくるとこれがとてつもなく気持ちが良い。しかし当然だが、女性はそうはいかないので数少ない沿線の施設のトイレを拝借することになる。どんな所でも都市を離れた奥地ではトイレに困るもので、モンゴルに限らずこの問題はどこでも同じだ。
ダランザドガドは、稚内あたりの緯度に位置する。平坦な砂漠が続くだけと思っていたら、岩を切り裂いた溪谷や、砂丘などがあり実に変化に富んでいる。大陸でしか見ることの出来ないダイナミックな風景に浸るため、外国からのネイチャーツーリストも大勢来ていた。
その宿であるツーリストキャンプへと入る。このキャンプ、遠くから見るとアメリカ映画の西部劇に登場する砂漠の町とまるで変わらなく見える。丸太小屋のバンガローや伝統的な住まいのパオが寝室で、中央に食堂や娯楽室などがある。我々はバンガローに泊まった。シャワーの遠慮がちに噴き出るぬるま湯で汗と張り付いた砂を流し、体はすっきりとした。
さて食事である。基本は肉料理。モンゴル人は本来農耕をしないため、かつては穀物での栄養摂取を行わず、乳製品と肉に頼るだけで野菜も食べなかったという。私たちが食べた肉は、ヒツジとヤギと牛・・・と説明を受けるが、皆同じような味で区別がつけにくい。しっかりと煮込んでいるのと、牛も羊も同じ草を食べて成長しているためか、草っぽい味がする。中国やインドのように、濃厚な香辛料に頼った味付けはしない。素朴で単純である。魚と肉の違いはあれ、味付けの素朴さは日本に似ているともいえる。
モンゴルは国土が日本の4倍。人口は300万人。茨城県と同じ数の人がこの広大な草原の上に住んでいる、と書きたいいところだが、半数の人は近代都市である首都ウランバートル周辺に住んでいる。
産業は、地下鉱物資源が最大の収入で、ヤギの冬毛であるカシミヤ、そして白鵬を代表する海外出稼ぎ組の送金である。それ以外はあまりない。ロシアに従って世界で二番目の社会主義革命を起こし、近代化と1990年から始まった民主化のため、公害、水不足、スラムなど発展途上国の抱える問題を一通り抱えている。
草原の民であるモンゴルの人は、農耕を発明した中国人の価値観とは全てが違うと言ってよい。遊牧民は古来より物を蓄えるという習性はなく、物を蓄えるための都市というものも必要がなかった。司馬遼太郎は「モンゴルは気体のようで、容易に固体にはなって行かない。」と草原の記の中で書いている。8日間のモンゴル探鳥ツアーは、この刺激的な言葉を幾分でも噛み締めることができる旅行になってくれたようで、実に面白い体験となった。
( 2016年10月11日投稿 )
-
前の記事

酒蔵を観光の拠点に! by 野﨑 光生 2016.10.02
-
次の記事
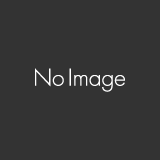
画聖が紡ぐ旅先の出会い ~長野県伊那市高遠町へ~ by 野﨑 光生 2017.01.29