坂口安吾文学に触れる旅 by 菊地 正浩
- 2014.07.25
- 地歴と旅(KK)
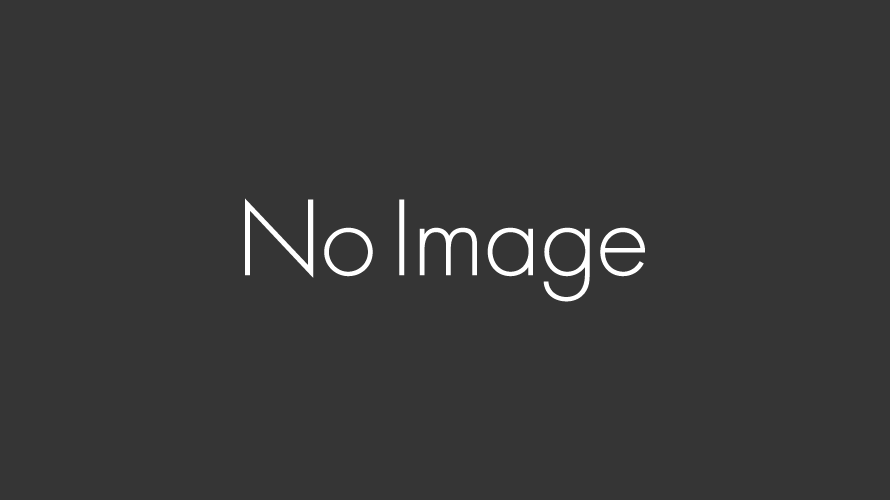
新潟県十日町市松之山は県の南西部、南は長野県に接し豪雪地帯である。
渋海川が西寄り、越道川と東川が東寄りを北流。地名は旧郷名を継承し、越道川上流の谷合にある鷹ノ湯、鏡ノ湯、庚申ノ湯の三つを総称して松之山温泉郷がある。
昭和37年の地滑り前後に、旧時代の地滑り地を開墾した「千枚下り」と称する棚田は、山奥にひっそりとたたずみ、当地区一の広さと美観を誇る。
○坂口安吾記念館(庄屋の館・財団法人大棟山美術博物館)
明治39年(1906)新潟県西大畑町で生まれる。東洋大学を卒業し無頼派作家、新戯作派と呼ばれた昭和時代を代表する流行作家。戦後文学の突破口を作ったと言われる。戦後の大地主、大知識人であった父親、坂口仁一郎の子として生まれ、炳五(へいご)と名付けられた。後に自ら炳五の名を捨て安吾と名乗るが、どうして安と吾の字を当てたのか。吾(われ)にこだわり、安は音感から暗と重なる。暗やみを行きつ戻りつして迷いつづける吾は悟でもある。求めても得られぬもの、激しく吾にこだわる限り、永遠に悟りには届かない。「こういう矛盾は私の一生の矛盾であり、その運命を私は常に甘受してきたのである。」(魔の退屈より)と記している。


○坂口の言う「人間」とは。
多くの著作の中、観念的な作風「吹雪物語」、ファルス(笑戯)の「風博士」などを経て、1946年に「堕落論」を発表。昭和30年(1955)脳出血により48歳の若さで急逝する。坂口安吾はよく「人間」と書いている。そして「人間は生き、人間は墜ちる」と言う。
あえて「人間」と表現するのは何故なのか?この人間とは何なのか?誰が言い出したのか?哲学を述べるつもりはないが、哲学的な書物の表現を思い出してみると、和辻哲郎は「人と人との間柄である」という、あまりにも単純すぎる。西田幾太郎は「精神と物体の区別はない」という、動物や物体には精神がないというのか。福沢諭吉は「上下の差別なく、万物の霊たる身と心との働きを以って天地の間にある」という。
天地の間に作られた人間をどう扱うのか。筆者の勝手な哲学からすれば、神仏と万物、自然の間に位置する人だけが人間であり、決して「猫間」「犬間」とは言わないと思う。
坂口安吾は福沢諭吉の哲学に多少とも影響を受けたのかもしれない。勝手な思いを巡らせながら、坂口安吾の文学世界に触れられる一時である。
○安吾文学碑
昭和62年(1987)、坂口ファンにより松之山小学校校庭に建立された。円熟期のレリーフ、小説「黒谷村」の冒頭文が碑に刻まれている。傍らにあるブナには、小学生により巣箱が架けられてある。昨年、ブッポウソウのヒナ4羽が誕生、監視カメラを設置して成長ぶりを観察していた。順調に生育していた時、アオダイショウが3羽を食べてしまった。子供たちは悲しんだが、先生はこれも自然の法則、摂理と教えたそうだ。


( 2014年7月25日 寄稿 )
-
前の記事
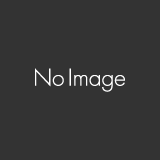
隠れキリシタンの郷 by 菊地正浩 2014.06.05
-
次の記事
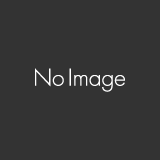
「美人の女将さんのいる店」 by 小川 金治 2014.08.10