隠れキリシタンの郷 by 菊地正浩
- 2014.06.05
- 地歴と旅(KK)
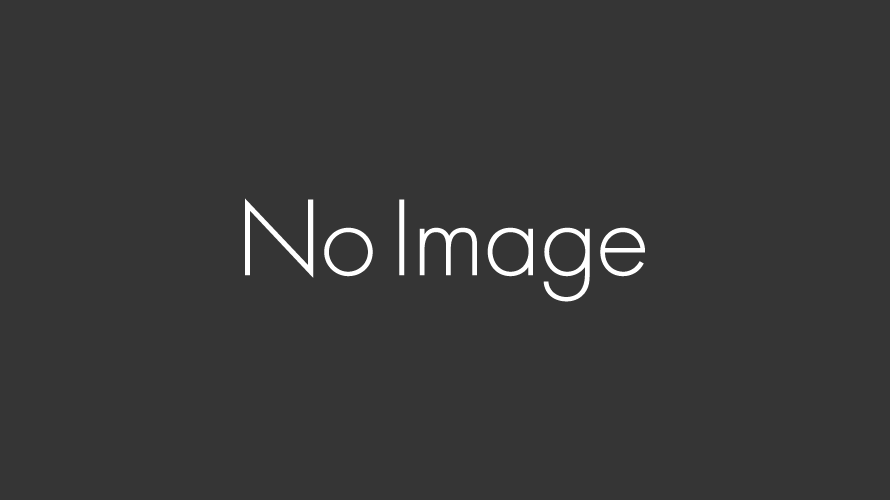
新潟県十日町市松之山湯山。東頸城丘陵と魚沼丘陵を東西に横切る山間路。
南北朝期、新田義貞、上杉謙信などの支配を受けてきた。越前、越中、越後三国以前は、越国(こしのくに・高志国、古志国)とも表記。中央政権からは山々を越えていくところ、あるいは琵琶湖や日本海を舟航して辿りつく、州島同然の土地から命名されたとの説もある。
町史によれば北越戊辰戦争、天明の悪作、飢饉などで、この頃の平和な時期は40年ほどであった。当時の死失人数書上帳には各村々での飢人が多数記されている。


< 松蔭寺のマリア観音 >
江戸幕府によって迫害や弾圧を受けたキリシタンは、人目を忍び隠れて信仰を貫き通した。巧妙なマリア観音や子育て地蔵を作り、それをマリアと信じて信仰の火を守り続けたという。湯山の松蔭寺には、我が国でも三体しかないと言われる、貴重なマリア像が所蔵されている。何時もは無人の寺で、地元の人が寺の管理と墓守をしている。毎年、お盆の一週間のみお坊さんが来て寺を開け、マリア観音を拝める。


郷の端にある民俗資料館の管理をしている前田さん(京都から移り住んだ)曰く、「隠れキリシタンの実態はいまだに判らない。いつ頃、何処から、何人ぐらいが来て住み着いたのか」。日本の原風景が残る長閑な山村である。集落を見わたしても人影がなかった。
民俗資料館に展示されている民俗資料には、豪雪地帯特有の農機具に混じり、縮布の生産が盛んであったことが判る。また、手漉き和紙の簀桁もあるので、和紙の生産が行なわれていたことも判る。隣村の牧村は楮の産地として知られ、松代(まつだい)も和紙の生産が盛んであった。隠れキリシタン達は、「千枚下り」という棚田を作り、農業の傍ら豪雪の冬には副業として縮布、手漉き和紙の生産をしていたのである。



( 2014年6月5日寄稿 )
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
旅ジャーナリスト会議
年次総会、創立12周年記念講演、懇親会のお知らせ
旅ジャーナリスト会議は今年創立12周年を迎えることとなりました。この間、会員は絶え間なく活動を続けてきましたが、会の活動を理解してくださる皆様に多大なご支援を頂きました。ここに改めて感謝申し上げます。
東日本大震災から3年、この災害と関係地域への旅との関わりについては、なお明るい日差しが射してきたとは言いがたい状況にあります。今回は菊地正浩会員の見聞を基に観光資源、エネルギー、復興施策について考えます。
会員はもとより、旅、観光、地域交流、町おこし、自然エネルギーなどに関心のある幅広い分野の方々にお出かけいただきたくご案内申し上げます。
万障お繰り合わせのうえ、ご出席賜りますようお願い申し上げます。
2014年5月吉日
記
日時 2014年6月21日(土)
受付 午後1時30分から
総会 午後2時から
講演 午後2時30分〜4時 (質疑応答時間を含みます)
講演会終了後、名刺交換会
会場 大井町駅東口前「きゅりあん」5F 第一講習室
JR京浜東北大井町駅・東口駅徒歩1分
東京都品川区東大井5−18−1 ℡(03-5479−4100)
講師 菊地正浩会員
講演 「 1:東北に元気を!蘇れ福島県
2:気仙沼・釜石の取材旅行から 」
表題に関わる写真をパワーポイントでビジュアルに紹介し、究極の観光資源「自然環境」を守る立場を明確にし、特に風力発電、地熱発電、巨大防潮堤のあり方について考えます。
懇親会 17時30分〜 懇親会場については当日ご案内します。
会費 6,000円(懇親会費を含む。講演会のみ出席の場合 1500円)
■お申込先 旅ジャーナリスト会議
事務局 小川金治
〒140-0013 東京都品川区南大井6-18-1-1126 小川写真事務所内
TEL/FAX:03-3762-4961
-
前の記事
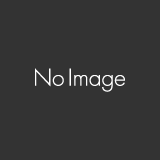
日本三大薬湯 松之山温泉の地熱発電を考える by 菊地正浩 2014.04.22
-
次の記事
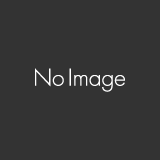
坂口安吾文学に触れる旅 by 菊地 正浩 2014.07.25